こんにちは。就労継続支援B型事業所 明石ぜろぽじです😊
今回は「運動」ってなんで必要なんだろう?を科学的根拠からお伝えできたらと思います。
■ なぜ「運動」が注目されているのか
厚生労働省は、がん・心疾患などと並んで「精神疾患」を日本の“5大疾病”の1つに位置づけています。
その中でも特に深刻なのが「うつ病」。世界保健機関(WHO)によると、2030年には“世界で最も社会的損失の大きい疾患”になると予測されています。
そんな中、薬やカウンセリングだけでなく、「運動」がうつ症状の改善に有効だという研究が世界的に増えています。
日本ではまだ研究数が少ないものの、海外ではすでに医療ガイドラインにも運動療法が正式に採用されています。
■ 海外ガイドラインに見る運動療法の位置づけ
イギリスの国立医療技術評価機構(NICE)は、軽度〜中等度うつ病の治療法として週3回・1回45〜60分・約12週間のグループ運動を推奨しています。
日本うつ病学会のガイドライン(2012)でも、初めて「週3回以上、中等度の運動を一定時間続けること」が推奨項目に加わりました。
■ 運動でどのくらい良くなるの?
世界的なコクランレビュー(2012)では、18歳以上のうつ病患者を対象にしたランダム化比較試験(RCT)32件を解析。
結果、運動による抑うつ改善効果の大きさ(SMD)は−0.67。
これは統計的に「中程度の効果」と評価され、薬物療法にも匹敵するレベルでした。
つまり、「体を動かすこと」は、心の治療として“確かな選択肢”であることが示されています。
■ どんな運動が効果的?
● 有酸素運動
ウォーキング・ジョギング・サイクリングなど、心拍数を上げる運動が最も安定して効果を示します。
中等度の強度(少し息が弾む程度)が最も推奨されています。
● 筋力トレーニング
高齢者では、レジスタンス運動(筋トレ)や、筋トレ+有酸素運動の複合プログラムも有効とされています。
効果量はいずれも「中等度〜高め」で、身体機能の向上にも寄与します。
● ヨガ・ストレッチなどの低強度運動
著者自身の研究では、10分間のヨガストレッチでも中高年女性の抑うつ症状と睡眠の質が改善しました。
また、ストレッチ実施後にはストレスホルモン(唾液中コルチゾール)が減少することも確認されています。
✅ ポイント: 「激しい運動」よりも、「短時間・低強度」でも継続できる運動が現実的で効果的。
■ 1回の時間と頻度の目安
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 頻度 | 週3回以上 |
| 時間 | 1回あたり10〜45分 |
| 強度 | “少し息が弾む”程度(中等度〜低強度) |
| 継続期間 | 10〜12週間以上が理想 |
短時間でも習慣化することで効果が積み重なります。
「続けられること」が最も重要です。
■ なぜ運動で気分が良くなるの?
論文では、複数の生理・心理メカニズムが紹介されています。
| 仮説 | 内容 |
|---|---|
| モノアミン仮説 | セロトニン・ドーパミンなど神経伝達物質のバランス改善 |
| エンドルフィン仮説 | “ランナーズハイ”のような快感物質の分泌 |
| 自己効力感仮説 | 「できた!」という達成感が自信につながる |
| 気晴らし仮説 | ネガティブ思考から意識を切り替える作用 |
| 体温仮説 | 体温上昇がリラックス反応を促す |
さらに、脳科学的には運動後に前頭前野の血流が増加し、認知機能の改善にも寄与することが確認されています。
■ 注意点と今後の課題
- 過度な運動は「運動依存」を招き、逆に気分を悪化させることも。
→ 無理せず、心地よい範囲で行うことが大切。 - 日本ではまだ大規模な研究が少なく、今後は日本人を対象にしたガイドラインの整備が求められています。
■ まとめ:心が疲れたときこそ、体を少し動かす
運動は「こころの薬」にもなる。
これは多くの研究が裏付ける科学的事実です。
うつ症状があるとき、「やる気が出ない」「動けない」と感じるのは自然なこと。
でも、10分のストレッチから始めても意味がある。
“がんばる運動”ではなく、“やさしく動く”ことが、心と体の回復を支えます。
日本ではまだ「運動=体の健康」というイメージが強いですが、これからの時代は「運動=心の栄養」にもなります。
あなたのペースで、あなたのリズムで。
体を動かすことが、きっと心を軽くしてくれます。
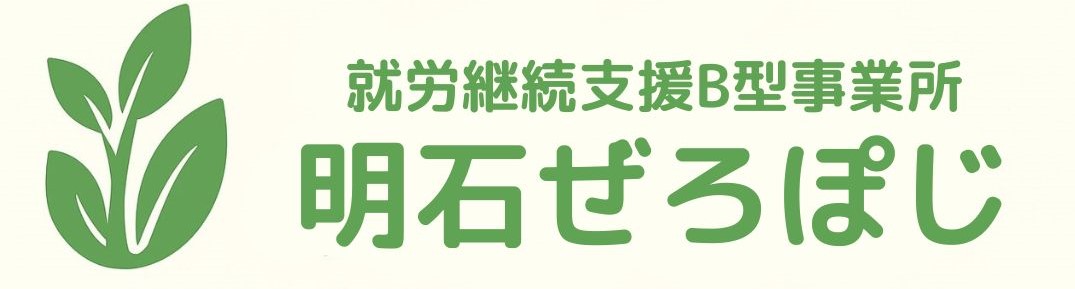





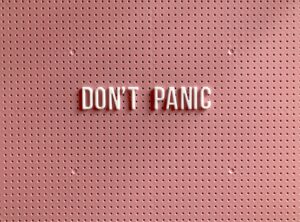



コメント