こんにちは。就労継続支援B型事業所 明石ぜろぽじです😊
あなたは「過食」の症状で悩んだりしたことはありませんか?
「過食」には大きく分けて2種類あります。
- 過食症(神経性過食症:BN) は、過食したあとに嘔吐や下剤の使用といった「代償行為」を伴うのが特徴です。
- 過食性障害(BED) は、代償行為を伴わず、過食が繰り返される状態を指します。
どちらも「自分でコントロールできない食行動」が中心にあり、生活の質や健康に大きな影響を与える深刻な摂食障害です。
どのくらい食べると過食になるの?
医学的には「過食」とは、通常の人なら食べきれないほどの量を、短時間(2時間以内)に食べてしまうことを指します。
例としては:
- 一度にラーメン3杯とデザートを食べきる
- スーパーの惣菜を複数買って一気に食べてしまう
など、「明らかに普通ではない量」と考えてOKです。
さらに重要なのは「コントロールできない感覚」を伴うこと。
「食べ始めたら止まらない」「お腹いっぱいでもやめられない」といった体験が典型的です。
どのくらいの頻度で起こると診断される?
診断基準(DSM-5)では:
- 過食性障害(BED) → 週1回以上の過食が3か月以上続く
- 神経性過食症(BN) → 週1回以上の過食と代償行為が3か月以上続く
つまり「たまにする食べすぎ」ではなく、慢性的に繰り返される状態が病気として扱われます。
発症の原因は?
過食症や過食性障害の原因は1つではなく、複数の要因が重なって発症すると考えられています。
心理・社会的要因
- ダイエットや体型への強いこだわり
- 「痩せなければいけない」という社会的プレッシャー
- ストレスや孤独、不安を食べることで解消しようとする
生物学的要因
- 脳の報酬系(快感を感じる回路)や衝動抑制の仕組みに異常がある
- セロトニン・ドパミンなどの神経伝達物質のバランスの乱れ
- 遺伝的な要因(家族に摂食障害や精神疾患がある場合、発症リスクが高まる)
身体的要因
- ホルモンの働き(グレリン=食欲増進、レプチン=満腹ホルモン)の不均衡
- 腸内環境(腸内細菌)が影響している可能性も報告あり
このように、「心・脳・身体・社会環境」が絡み合うことで発症します。
過食性障害の治療には何が効くの?
研究の結果、第一選択の治療は心理療法、とくに認知行動療法(CBT) です。
- 「食べすぎてしまうトリガー」や「考え方のクセ」を整理し、コントロール力を取り戻します。
- 対人関係療法(IPT)、弁証法的行動療法(DBT)も効果があり、オンラインやセルフヘルプ型のCBTも有効性が示されています。
薬物療法は?
- リスデキサムフェタミン(LDX) が唯一FDA承認薬(中等度〜重度のBED)。
- 抗てんかん薬や抗うつ薬は短期的に有効例もありますが、副作用や長期効果には課題があります。
- 薬はあくまで「補助的手段」として使われます。
新しいアプローチも登場している
- オンラインCBTやアプリ
- 体重管理と組み合わせた統合プログラム(HAPIFED)
- 新薬候補(ナルトレキソン+ブプロピオンなど)
- 順次介入モデル(SMARTデザイン)
研究は進んでおり、治療の選択肢は広がっています。
まとめ
過食症や過食性障害は「単なる食べすぎ」ではなく、量・頻度・コントロール不能感を伴う深刻な病気です。
発症には心理・社会・脳・身体の要因が複雑に関わり、治療はCBTを中心に薬や新しい方法も加わりつつあります。
もしあなたや身近な人が「過食」に悩んでいるなら、「たまの食べすぎ」とは違うかもしれないと気づくことが第一歩。
そして、早めに専門家へ相談してみることをおすすめします。
目次
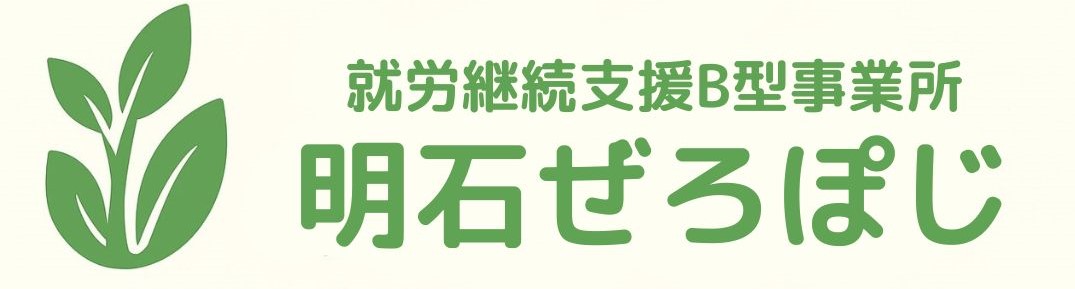









コメント