こんにちは。就労継続支援B型事業所 明石ぜろぽじです😊
なぜか疲れが取れない、、
睡眠は取れているはずなのになぜか辛い、、
などのお悩みを持つ方は少なくはないと思います。
今回はこれらに関する悩みを『分子栄養学』という観点から見ていこうと思います。
慢性疲労とは何か?
「寝ても疲れが取れない」「原因がはっきりしない倦怠感が続く」👉これが慢性疲労の特徴。
CFS(慢性疲労症候群)とは
・6か月以上続く強い疲労
・休んでも改善せず、日常生活や社会生活に支障が出る
・集中力低下、筋肉痛、頭痛、免疫異常などを伴うことも多い
単一の原因ではなく、感染後の免疫変化、ホルモンバランス、ストレス、栄養欠乏などが複雑に関与する問題となっています。
分子栄養学とは何か?
分子栄養学とは「体の分子レベルでの栄養状態」に注目し、細胞や代謝の不調を“栄養素の不足・過剰・バランス”から考える学問。
一般的な栄養学との違い
・一般栄養学 → 摂取カロリーや食事バランスの指導中心
・分子栄養学 → 血液検査や代謝状態を解析し、必要な栄養素を個別に最適化
“病気にならないため”ではなく、“不調を改善するため”に細胞レベルの栄養環境を整えるアプローチ
慢性疲労に対する食事療法のアプローチ
1.エネルギーを作るための栄養を満たす
慢性疲労の背景には「細胞がエネルギーを作れない」状態が隠れています。
そのために必要なのが ビタミンB群・マグネシウム・カルニチン・CoQ10。
- 赤身肉・レバー・卵 → ビタミンB群、カルニチン
- 魚(特にサバ・イワシ) → CoQ10、オメガ3
- ナッツ・葉物野菜 → マグネシウム
👉 ポイント:「肉・魚・卵・野菜」をしっかりバランスよく食べること。
2.酸化ストレスを抑える
慢性疲労では、体が「サビついた」ように酸化ストレスが溜まっています。
これを防ぐには 抗酸化ビタミンやポリフェノール が大切。
- カラフルな野菜や果物(ピーマン、ブロッコリー、ベリー類) → ビタミンC・カロテノイド
- 緑茶・カカオ(高カカオチョコ) → ポリフェノール
- ナッツ類(アーモンド・クルミ) → ビタミンE
👉 ポイント:「毎日いろどり豊かな食材を選ぶ」ことが抗酸化の近道。
3.ホルモンと神経伝達を整える
気分の落ち込みや睡眠の乱れも慢性疲労に多い症状。
その背景にあるのが トリプトファンや亜鉛 の不足。
- 大豆製品(納豆・豆腐) → トリプトファン
- 鶏むね肉・卵・バナナ → セロトニン合成を助ける
- 牡蠣・赤身肉 → 亜鉛
👉 ポイント:「大豆製品+魚介+卵」を組み合わせると神経の材料がそろう。
4.免疫と炎症を整える
慢性疲労はしばしば免疫の乱れや炎症が関与します。
ここで役立つのが オメガ3脂肪酸と腸内環境の改善。
- 青魚(サバ、イワシ、サーモン) → EPA・DHA
- 発酵食品(味噌、ヨーグルト、キムチ) → プロバイオティクス
- 海藻・きのこ・野菜 → 食物繊維で腸内環境を整える
👉 ポイント:「魚と発酵食品を毎日、野菜と海藻をしっかり」
まとめ
- エネルギーを作る栄養(B群、Mg、カルニチン、CoQ10)
- 酸化を防ぐ栄養(ビタミンC・E・ポリフェノール)
- 神経とホルモンを整える栄養(トリプトファン、亜鉛)
- 免疫と炎症を整える栄養(オメガ3、腸内環境)
→ この4つを意識して食材を選ぶことが、慢性疲労からの回復につながります。
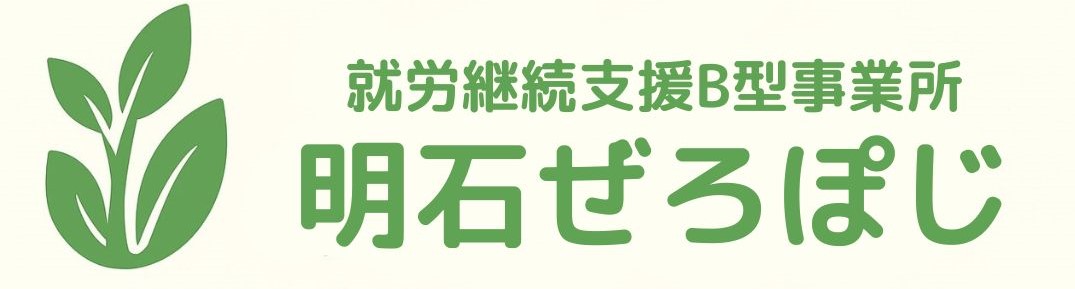









コメント