こんにちは。就労継続支援B型事業所 明石ぜろぽじです😊
皆さんは普段している「呼吸」に目を向けたことはありますか?
実は呼吸と精神状態には明確な関係があります。 特にうつ症状のある方は、無意識のうちに呼吸が浅くなったり、リズムが乱れたりしやすいことが、近年の研究で明らかになっています。
呼吸は自律神経と密接に関わっており、心理的な状態を反映する一つの指標として、また介入の手段として注目されています。
重度うつ症状における呼吸パターンの変化
2021年に発表された論文では、重度うつ病患者における呼吸パターンの変動性(Respiratory Pattern Variability:RPV)が健常者と比べて高く、不安定であることが報告されました。
具体的な特徴:
- 呼吸数の増加傾向
- 呼吸の深さとリズムが安定しない
- 特に夜間に変動が大きくなる
これらの変化は、自律神経系のバランスや情動制御機能の低下と関連していると考えられています。
呼吸を使ったアプローチの有用性
呼吸は、唯一意識的にコントロールできる生理機能です。 そのため、「動けない」「集中できない」といった状態へのアプローチ手段としても活用できます。
腹式呼吸やゆっくりとしたペースの呼吸は、交感神経の過緊張を緩め、副交感神経の活動を高めることが示されています。
短時間・低負荷で導入できる点からも、日常の活動に組み込みやすく、継続的な取り組みにも向いています。
呼吸を活用した具体的な取り組み例
たとえば、軽作業前に2〜3分間の呼吸調整を挟むことで、身体の緊張が緩み、集中力の向上や情緒の安定につながることがあります。
こうした“土台作り”が整うことで、その後の作業やコミュニケーションもスムーズになる傾向が見られます。

まとめ
呼吸パターンの乱れは、うつ状態における一つのサインであり、また介入ポイントでもあります。
今後、「からだ」から働きかける一つの手段として、呼吸への注目はさらに高まっていくと考えられます。
ぜろぽじでは、今後も身体的アプローチと心理的支援をつなぐ試みを積極的に取り入れていきます🧘
参照
Anesthesia & Analgesia 132(5):p 1206-1214, May 2021. | DOI: 10.1213/ANE.0000000000005478
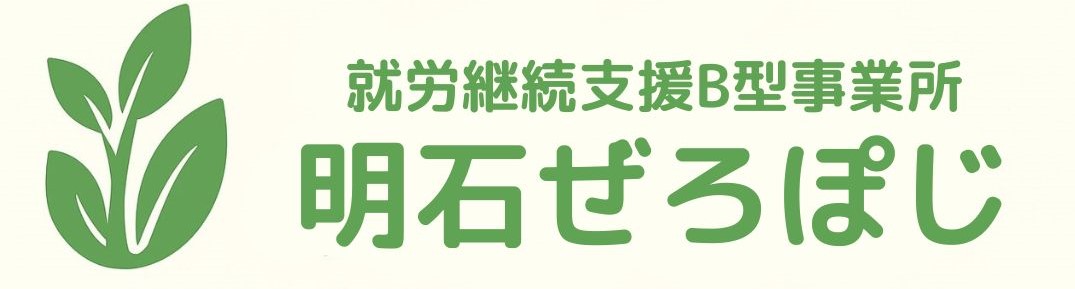









コメント