こんにちは。就労継続支援B型事業所 明石ぜろぽじです😊
今回は前回に引き続き「パニック障害」について取り上げます。
専門的な表現も出てきますが、今まさに悩んでいる方や、大切な人が悩んでいる方にとって、心が少しでも楽になるきっかけになれば嬉しいです。
パニック発作は突然起こるのか?
パニック障害は、「突然息ができない」「心臓が止まりそう」といった強烈な恐怖が、何の前触れもなく襲ってくる病気です。
一見すると心臓や呼吸の問題のように見えますが、実際には脳の中で 恐怖を処理するシステム が過敏に働いてしまうことが根本にあります。
扁桃体を中心とした「恐怖回路」の過敏性
恐怖の反応を生み出す中心は「扁桃体(amygdala)」です。
- 扁桃体は、外からの危険信号(音や映像など)や、体の内部からの感覚(心拍や呼吸の変化)を受け取り、それを「危険だ!」と判断すると自律神経やホルモン系に命令を出します。
- この回路が過敏になると、本来なら安全な状況でも「窒息するかもしれない」「倒れるかもしれない」と脳が誤作動を起こします。
さらに扁桃体は、青斑核(ノルアドレナリン中枢)、海馬(記憶・文脈学習)、前頭前皮質(状況判断)などと密接につながっており、これらが一斉に動き出すことで、動悸・発汗・息苦しさ・強烈な恐怖といった典型的なパニック発作が生まれます。
神経伝達物質のアンバランスが加わる
恐怖回路の過敏性に加えて、複数の神経伝達物質が異常に働くことも重要です。
1. ノルアドレナリン
- 脳の青斑核から放出されるノルアドレナリンは「危険だ!」という警報を全身に広げます。
- 過剰になると、動悸・震え・息切れなど、まさに「戦うか逃げるか(fight or flight)」反応を引き起こします。
2. セロトニン
- セロトニンは感情の安定に関わる物質ですが、パニック障害ではその調整機能が乱れていると考えられます。
- SSRI(抗うつ薬)がパニック障害にも効くのは、セロトニンの働きを安定させることで「過剰な恐怖信号」を鎮められるからです。
3. GABA
- GABAは脳内の「ブレーキ役」で、不安や興奮を抑える働きをします。
- パニック障害ではこのブレーキが効きにくい(GABA受容体の感受性低下)ことが報告されています。
- ベンゾジアゼピンが即効性を持つのは、このブレーキ作用を強化するからです。
4. ペプチド(CCK, CRF, NPY など)
- CCK:投与するとパニック発作を誘発することがあり、患者は特に過敏に反応する。
- CRF:ストレスホルモンを調整するが、過剰だと不安を高める。
- NPY:逆に不安を抑える作用があり、パニック障害患者では代償的に増加しているケースも。
相互作用の結果としての「パニック発作」
ポイントは、これらの要素が 単独で働くのではなく、互いに絡み合っている ことです。
- 扁桃体が誤って危険信号を発する
- ノルアドレナリンが全身を緊張させる
- セロトニンやGABAの調整力が弱いためブレーキがかからない
- CCKやCRFがさらに不安を煽る
この「悪循環」が一気に立ち上がることで、突然のパニック発作につながります。
治療は「回路の過敏性を和らげる」こと
1. 薬物療法 ― 脳の「化学的バランス」を整える
パニック障害は複数の神経伝達物質が関与するため、薬物療法はその調整を担います。
● SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
- 代表:パロキセチン、セルトラリン、エスシタロプラムなど
- セロトニンの働きを安定させることで「恐怖回路の暴走」を抑える。
- 即効性はなく、数週間〜数か月で効果が出る。
- 発作そのものだけでなく「また発作が起こるかも…」という予期不安も改善。
● ベンゾジアゼピン系(アルプラゾラム、クロナゼパムなど)
- GABAの作用を強め、「脳のブレーキ役」を回復させる。
- 即効性が高く、発作時の頓服としても有効。
- ただし長期使用は耐性・依存のリスクがあるため、短期・補助的に使うのが一般的。
● その他
- 三環系抗うつ薬・MAO阻害薬:古典的だが有効性あり。副作用が多く第一選択ではない。
- 新しい選択肢(研究段階):セロトニン-ノルアドレナリン作用薬、CCK受容体拮抗薬、CRF拮抗薬など。
⇒薬は「扁桃体や青斑核の過敏性を和らげるスイッチ」として働くイメージです。
2. 認知行動療法(CBT) ― 「恐怖の学習」を書き換える
薬で症状を和らげても、「恐怖条件づけ」が残っていると再発のリスクが高い。
そこで心理療法が重要になります。
● 暴露療法(エクスポージャー)
- 「発作=死ぬかもしれない」という学習を修正するために、段階的に恐怖状況に直面する。
- 例:電車に乗る → 息苦しさを感じる → 実際には死なない、という経験を積む。
- 扁桃体の「恐怖記憶」が更新され、過敏反応が減っていく。
● 認知再構成
- 「動悸=心臓発作」という誤った解釈を修正し、「ただの一時的な身体反応」と捉え直す。
- 前頭前皮質の働きを強め、扁桃体の暴走を抑制。
● 呼吸法・リラクゼーション
- 過換気(CO₂低下 → 脳内乳酸増加)が発作を誘発するため、腹式呼吸やマインドフルネスで自律神経を安定化。
⇒心理療法は「恐怖回路のソフトウェア修正」と考えると分かりやすいです。
3. 薬と心理療法の相互作用
- 薬だけ → 発作は抑えられるが、学習の修正が進まず再発リスクが残る。
- 心理療法だけ → 発作への耐性がつくが、強い不安時に続けるのが難しいことも。
- 併用 → 症状を薬で安定させつつ、CBTで恐怖記憶を書き換えるのが最も効果的。
研究でも、薬物+CBTの併用が再発予防に優れる ことが示されています。
まとめ
パニック障害の治療は、
- 薬物療法 → 回路の過敏性を鎮める(ハード面)
- 認知行動療法 → 誤った恐怖学習を修正する(ソフト面)
この両輪がかみ合うことで効果を発揮します。
将来的には、ペプチド系(CCKやNPY)を標的にした薬や、脳回路に直接作用する新しいアプローチが登場する可能性もあります。
参考文献
- Goddard, A. W., & Charney, D. S. (1997). Toward an integrated neurobiology of panic disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 58(Suppl 2), 4–11.
- Gorman, J. M., Liebowitz, M. R., Fyer, A. J., & Klein, D. F. (1989). A neuroanatomical hypothesis for panic disorder. American Journal of Psychiatry, 146(2), 148–161.
- Charney, D. S., & Deutch, A. (1996). A functional neuroanatomy of anxiety and fear: Implications for the pathophysiology and treatment of anxiety disorders. Critical Reviews in Neurobiology, 10(3–4), 419–446.
- Klein, D. F. (1993). False suffocation alarms, spontaneous panics, and related conditions: An integrative hypothesis. Archives of General Psychiatry, 50(4), 306–317.
- Roy-Byrne, P. P., Craske, M. G., & Stein, M. B. (2006). Panic disorder. The Lancet, 368(9540), 1023–1032.
- Bandelow, B., Michaelis, S., & Wedekind, D. (2017). Treatment of anxiety disorders. Dialogues in Clinical Neuroscience, 19(2), 93–107.
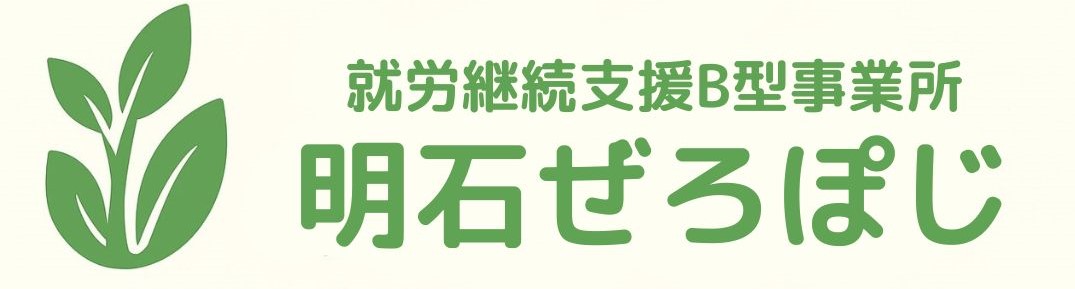









コメント