こんにちは。就労継続支援B型事業所 明石ぜろぽじです😊
「また発作が来るのでは…」そんな不安が頭から離れず、外出や人との交流さえも怖くなってしまう。
パニック障がいはとてもつらい病気ですが、克服する道があります。
薬に頼るだけでなく、考え方や行動のクセを少しずつ修正していく 認知行動療法(CBT) は、世界中で有効性が認められ、多くの人の生活を取り戻す手助けをしています。
目次
1. 認知再構成(Cognitive Restructuring)
- 目的:
パニック発作時の「破局的な思考(catastrophic misinterpretation)」を修正すること。 - 典型的な誤った認知の例:
- 「心臓がドキドキしている → 心臓発作で死ぬのでは?」
- 「息苦しい → 窒息して倒れるのでは?」
- 「人前で発作が起こる → 恥をかいて人生が壊れる」 - やり方:
セラピストと一緒に、その思考を紙に書き出し「本当にそうか?」と検討する。
・動悸は運動やカフェインでも起こるが、命に関わらないことが多い
・過去の発作でも死んだことはなかった
・心電図や診察で異常がないなら過剰な恐怖かもしれない
→ こうした事実を積み重ねることで「体の反応=必ず危険」という思い込みを修正していく。 - 効果:
発作が起きても「死ぬのでは」ではなく「これは一時的な体の反応」と捉えられるようになり、不安のスパイラルが断ち切られる。
2. 曝露療法(Exposure Therapy)
- 目的:
「恐怖を避ける → 短期的には安心だが、長期的に恐怖が強化される」という悪循環を断つ。 - 回避行動の例:
電車に乗らない、人混みを避ける、外出を控える、運動を避ける(動悸が怖いから)。 - やり方:
階層表(恐怖の程度を10段階などで分けるリスト)を作り、低いレベルから段階的に挑戦する。
例:
1. 近所のコンビニに入る(軽度の不安)
2. 電車の1駅分だけ乗る
3. 映画館に座ってみる
4. 混雑したショッピングモールに30分滞在
→ 徐々に「不安があっても大丈夫」「発作は必ず収まる」と学習する。 - 効果:
回避が減り、生活の幅が広がる。恐怖対象に対して「慣れ(habituation)」や「安全学習(safety learning)」が起き、発作への恐怖が減少する。
3. 内受容曝露(Interoceptive Exposure)
- 目的:
「身体感覚そのものに対する恐怖」を弱める。 - 背景:
パニック障害の人は、自分の身体感覚(動悸、息切れ、めまいなど)を「危険のサイン」と誤って解釈する傾向がある(=内受容感覚の過敏)。 - やり方(セッション中に実際に行う):
- 過呼吸をして息苦しさを意図的に作る
- その場で走って心拍数を上げる
- 椅子をぐるぐる回ってめまいを起こす
- 息を止めて胸の圧迫感を体験する
これらを安全な環境で繰り返し体験し、「体の感覚は危険ではなく、自然に収まる」ということを体で学ぶ。 - 効果:
「動悸=死ぬ」という条件づけが弱まり、身体反応を過度に怖がらなくなる。
結果的に、発作が起きても「これは大丈夫」と受け止められるようになる。
まとめ
- 認知再構成:考え方を修正する(頭で理解する部分)
- 曝露療法:避けていた状況に慣れる(行動で学習する部分)
- 内受容曝露:身体感覚に慣れる(体で学習する部分)
薬だけに頼らない選択肢があるのであれば、それを実践して、症状の緩和に繋げることも福祉に関わるものとしてたいせつなことではないでしょうか。まずは『知る』という努力を今後も我々はしていきます。
参考文献
Panic disorder
Peter P Roy-Byrne, Michelle G Craske, Murray B Stein
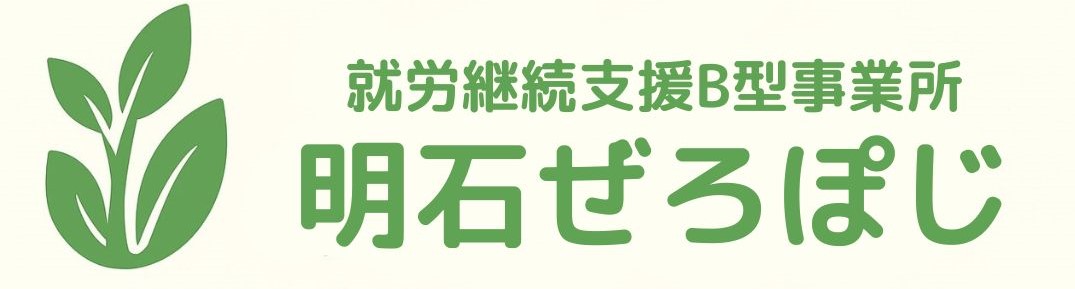
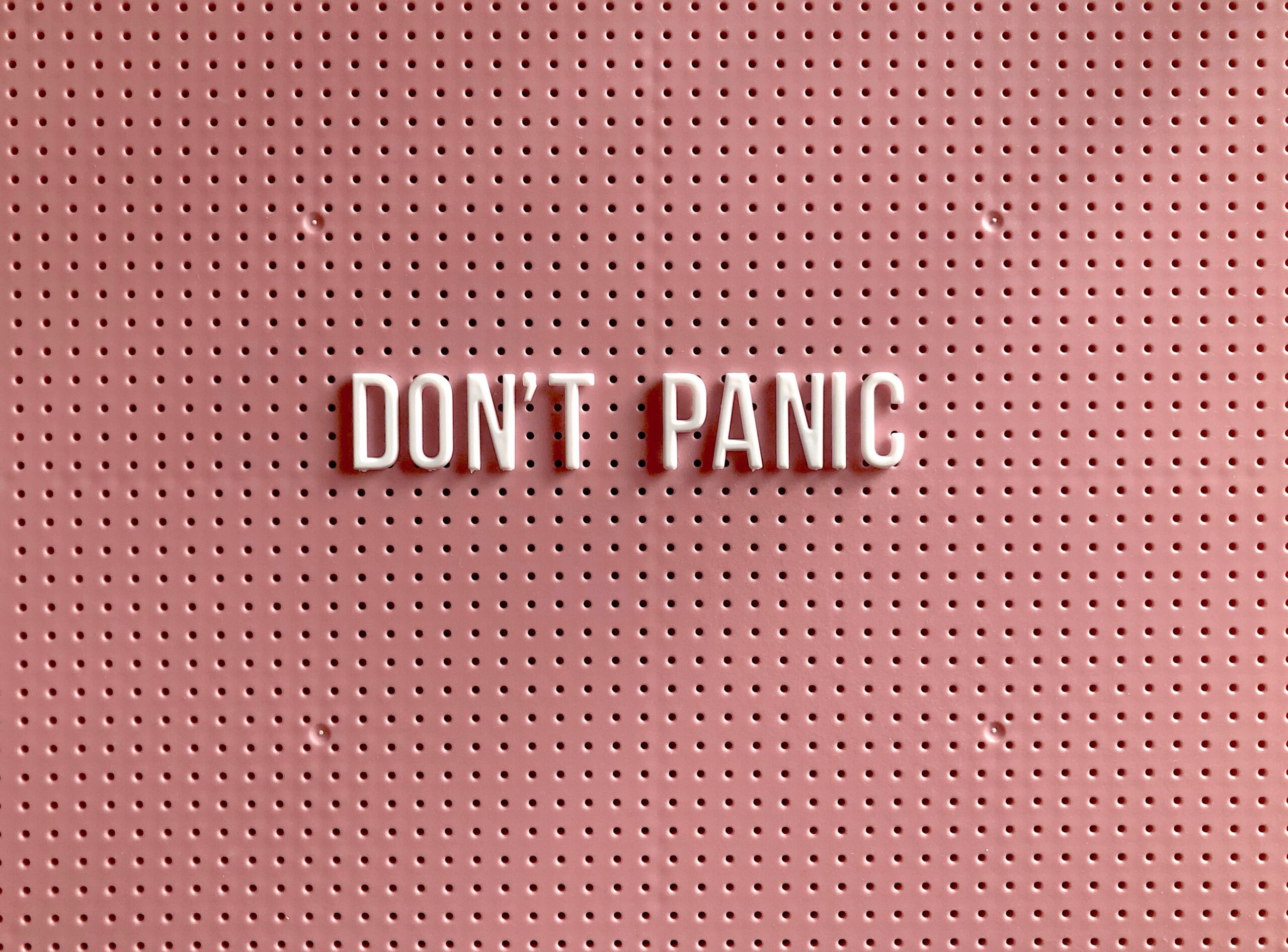








コメント